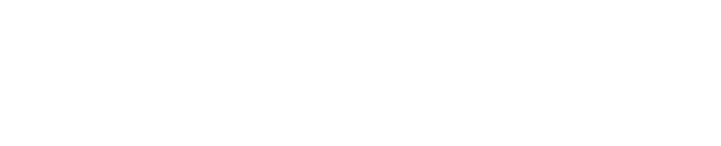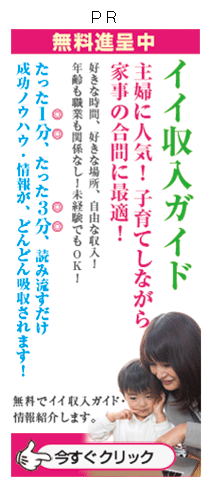こんにちは!せこぴんです。
最近引っ越しまして、家のお清めをしました。
色々なやり方はあると思いますが、私が行ったお清めの際に
必要な物のなかで、最重要だったのが「お塩」です。
気の出入り口をお酒とお塩で清め、そのあとに盛り塩を
しました。
今回は、私たちの生活に切っても切れない存在の
「お塩」について調べました。
塩と人類の歴史は大変古く、日本では縄文後期から弥生時代
初期に、塩が登場するといわれています。
世界では、メソポタミア、エジプト文明の頃には
すでに塩が使われていました。川近くで、死海や
塩湖があった地域で、文明が栄えていたことが
わかります。
ところで、サラリー(給料)の語源は塩を意味する
SALからきていることをご存じでしたか?
古代ローマの兵士の給料は塩(SAL)だった
のです。英語のsalaryの語源です。
日本では「塩=神」という考え方があります。
太陽が海水を乾燥させてできるものが塩ですが、太陽(火)
と海水(水)、すなわち、か(火)とみ(水)=神となり、
塩は神だというわけです。
ひと言で塩といっても、原料、採掘場所、製法、ミネラル
の含有率(添加)などによって、細かく分類されます。
①食卓塩
食卓塩も塩の一種類ですが、どんな季節でも固まらず
手軽にパラパラと振りかけられる便利さが、その特徴
です。これは、塩化ナトリウム99%以上のものに、
炭酸マグネシウムを添加した精製塩です。食卓塩には
グルタミン酸ナトリウム(昆布のうまみ成分)が加わって
います。ミネラル分はほとんどありません。
②海水塩
日本をはじめ、世界の海に面した多くの国で海水を原料
に作られています。海水を塩田から濃縮し、太陽光と風
だけで数か月かけて結晶化した非加熱の完全天日塩や、
平釜で煮詰めて結晶化させた平釜塩や、輸入した原塩に
にがりなどのミネラルを加えて作られたものがあります。
②岩塩
大昔、海だった場所が地殻変動で陸地に閉じ込められて
塩湖となり、その海水の水分が蒸発して塩が徐々に結晶化
してできた塩の層から採取したもの。
ヒマラヤの岩塩などは有名。
③湖塩
地殻変動によって陸上に閉じ込められた海水が、長い年月
をかけて濃縮されてできた塩分濃度の高い湖、もしくは
地中の岩塩が雨水や地下水で溶けて湖になったものから
作られた塩。
【塩の効能】
高齢化社会、かつ若年層はストレスフルな生活で慢性病が
社会問題となっています。中でも、高血圧はしばしば話題
になる疾病で塩分控えめが常識になり、塩が敵視される
風潮にあります。でも、本物の塩と塩化ナトリウム99%
の食塩とは全く作用が異なります。
塩化ナトリウムは血液のミネラルバランスを崩し、血流が
悪くなるので身体は一生懸命に体の隅々まで血液を届け
ようとするので血圧が上がります。
一方、本物の塩は血行
を良くして新陳代謝を上げてくれます。
塩の効能をまとめてみましょう。
●免疫力アップ・・・海の塩に含まれる豊富なミネラル分は
インフルエンザなどのウィルス性の病気の予防になります。
●ストレスをコントロールする脳内ホルモンであるセロト
ニンとメラトニンは、ストレスで鬱になると分泌が弱まり
ます。ところが塩の摂取で、努力無しでこれらの幸せ
ホルモンを分泌してくれます。
●喘息を和らげる・・・塩は天然の抗炎症成分です。医者に
よっては、ぜんそく患者でステロイド吸入薬がないときは、
塩を舐めることを勧める医者もいます。
●殺菌効果・・・漬物や梅干しや保存食では塩が欠かせない
ように、塩には強い殺菌効果があります。アトピーや虫刺
されなどにも効果がある。
血液の塩分濃度は海水の塩分濃度とほぼ同じです。
また、生き物を作る元素と海水が含む元素は極似して
います。また、赤ちゃんが誕生までに過ごす羊水のミネラル
バランスが海水と似ています。
本物の塩には、海水の持つミネラルをそのまま凝縮させた
ものが含まれているので、人間にとってこれほど馴染みが
良いものはないのです。私たちの身体自体が海のミネラルで
構成されているのですから、それらのミネラル無しで健康
に生きていけるわけないのです。
【塩と美容】
ミネラル成分が豊富な塩は肌にも良いと言われています。
特に、バスソルトやマッサージ用として人気があります。
塩をお風呂に入れると、お湯がなめらかになり抹消血管
の血行が良くなるので身体の芯から温まります。
保湿効果も高まり、疲労回復や風邪予防にも効果
がありますし、精油を入れるとリラックス効果も
高まります。また、頭皮や顔のマッサージにも塩は
効果的です。塩の成分が頭皮の毛穴に詰まった脂分
を溶かし出し、頭皮の匂いを取ってくれます。
もちろん、ここで使うのは不純物や有害物質を含ま
ない無添加のものを選びましょう!
人間の体は、塩なしでは生きられません。
でも、本物の良い塩を選び、適量を摂取して
行きましょう。
せこぴん
最新記事 by せこぴん (全て見る)
- シードルについて - 2021年7月13日
- 成功のために必要なものをオールインワンで効率的に学びましょう - 2021年7月7日
- LUREA で本物の知識と稼ぐ方法をゲットする - 2021年7月2日