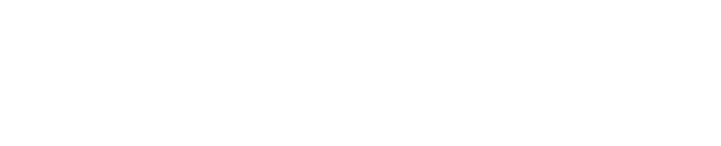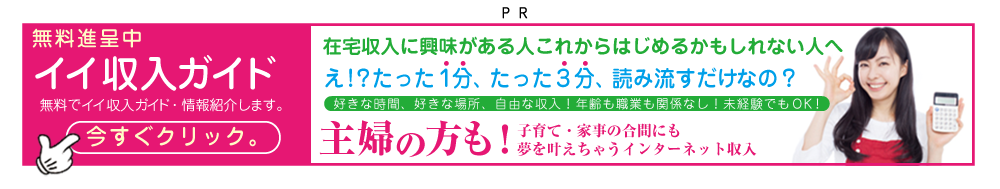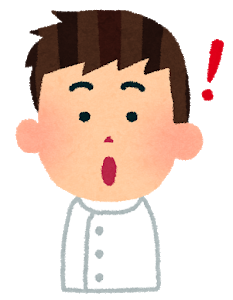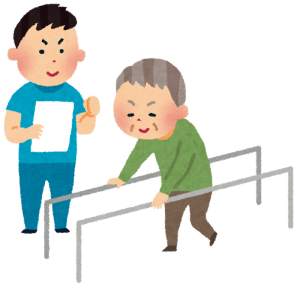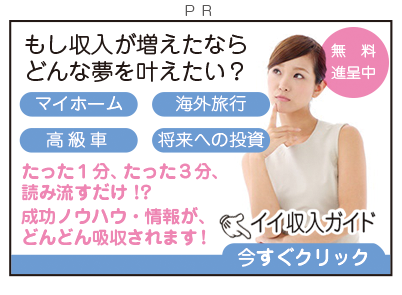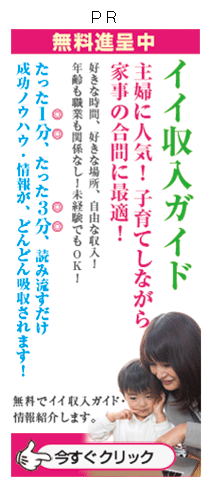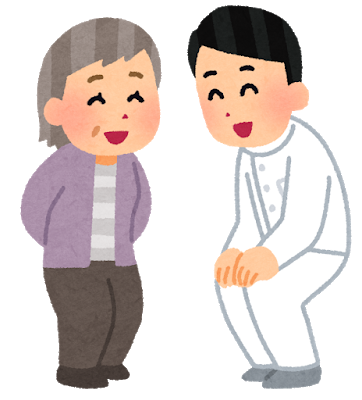
こんにちは!
今回は、私が働いている分野、「訪問リハビリテーション」についての記事です!
在宅でのリハビリテーションと言えば他に通所リハビリテーションがありますが、訪問と通所ではどの様な違いがあるのでしょうか?
今回は、通所リハビリテーションとの違い、メリット、受けられる対象者の基準を解説していきます!
どのような時に利用すればよいの?
訪問リハビリは、デイケアではできないリハビリを希望する場合などに利用します。
例えば「家の中を一人で歩きたい」「自宅のお風呂の浴槽が跨げるようになりたい」「今までみたいに料理が作れるようになりたい」「スーパーまでの道を安定して歩けるようになりたい」など、実際の環境におけるリハビリが望ましい場合、実際に家に来てリハビリをする訪問リハビリが適切です。
また、寝たきりでデイケアに通えない方に麻痺や関節の拘縮(こうしゅく)改善のリハビリを行ったり、食事のムセや飲み込みの悪さに対して訪問リハビリを利用することもできます。
【注意点】
訪問リハビリを利用するには、主治医の指示が必要です。
まずはケアマネジャー、主治医に状況を伝え、利用について相談してみましょう!
訪問リハビリテーションとは?
訪問リハビリテーションとは、理学療法士や作業療法士や言語聴覚士といった国家資格を持つリハビリ専門員が利用者様の自宅へ訪問し、主治医の指示に合わせてリハビリテーションや療養上のケア、診療の補助などを行います。
【厚生労働省の定義】
居宅要介護者について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常 生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション。
訪問リハビリの目的は身体機能の向上だけではなく、利用者様の日常生活における自立と社会参加の促進、また利用者様とその家族を含めた心理的サポートも含まれ、QOL(Quality of Life:人が人間らしい生活をおくること)の支援を総合的に行います。
継続したリハビリを受けたいけれど様々な理由から通院するのが難しい方や、自宅でのリハビリ方法や家族が介助する時の方法を指導してもらいたい方などは、ぜひ、訪問リハビリを利用してみてくださいね!
訪問リハビリテーションは誰が受けられる?
厚生労働省の定義
通院が困難な者とされています。
「通院が困難な利用者」の趣旨は、通院により、同様のサービスが担保されるのであれば、通所系サービスを優先すべきとされているからです。
つまり、通院できる人は、通院を優先させるので訪問リハビリテーションは当てはまらないということになります。
また、訪問リハビリテーションを受けられる対象者は、
1)介護保険証の認定を受けられている方
どんな病気や怪我がきっかけであっても要介護認定(要介護1~5)を受けている方。
また、40~64歳までの方については、要介護状態となった原因が、「がん」や「関節リウマチ」など「16種類の特定疾病による場合」の認定を受けた方のみが対象となります。
介護予防(1~2)の方は、「介護予防訪問リハビリテーション」の対象となり、同様のサービスを利用することができます。
2)かかりつけ医から「訪問リハビリテーションが必要」だと認められた方
家庭内の環境や病状の内容から診て、医師が必要だと診断した場合に訪問リハビリテーションを受けられることになります。
この場合は、主治医に指示書を書いていただく際に明記してもらいます。
具体的に訪問リハビリテーションでは何をする?
ご自宅の環境に合わせて、実際の生活が少しでも改善できるよう、以下のようなリハビリテーションを行います。
健康管理
血圧や脈拍、体温測定、食事や排せつなどの確認、管理など
身体機能向上、維持のための訓練
筋力トレーニング、関節硬化を防ぐための関節可動域訓練など
日常生活の動作訓練
歩行訓練、トイレの訓練、嚥下訓練、発声訓練など
生活環境の整備
手すりの設置や段差の解消といった住宅改修の助言など
福祉用具選定
適切な福祉用具の提案など
ご家族からの相談対応
介助方法の指導や助言など
具体的なリハビリの例として、
・基礎体力をつけるための運動
・実際のトイレまでの行き来を練習したり、屋内・屋外へ安全に移動するための練習など
・安全に自宅内を移動するための福祉用具を考えたり、家具の配置を変えたり、家族が介助する上での工夫やコツをアドバイスすることもあります。
少しでも、リハビリについて知ってもらえたら嬉しいです^_^
ちりつも
最新記事 by ちりつも (全て見る)
- アフィリエイトで重宝するSIRIUSのことを調べてみました - 2023年2月5日
- 初心者におすすめ!月数万円のお小遣いを稼ぐ方法とは? - 2022年10月17日
- - 2022年1月12日